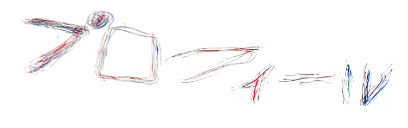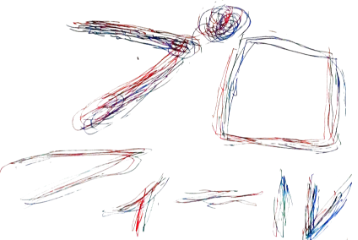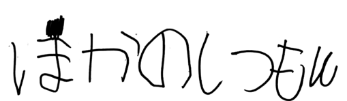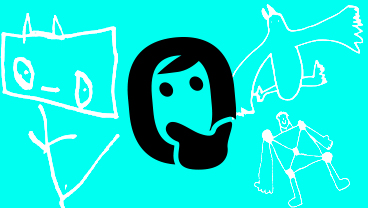ブラジル・エステーヴァン村

人口300人のブラジルの漁村で
2000年に保育園を開園
ほかにも違いはまだまだある。エステーヴァン村の夜は、プラネタリウム並の星空が広がるそう。
「『なんでこんなにいろんな色の星があるんだろう? 大きさが違うんだろう?』園の子どもたちからはそんな質問をよく受けます。それと、満月の灯りがそれだけで暮らせるくらい明るいので、『本当は太陽よりお月さまの方が明るいんじゃない?』なんて言う子もいました」
エステーヴァン村から徒歩10分ほどのところには、観光地が広がっている。コロナ禍を経て、とくにカーニバルのシーズンは、おもにヨーロッパからの観光客が多く訪れた。
「イタリア人、フランス人、オランダ人が多いんですが、子どもたちから言わせると、彼らが話している言葉は、たまにポルトガルと似た響きの単語があるから少しだけわかるそうなんです。ただ、私がたまに日本語を話しているのを見ると一言もわからないから、『真由美はどこから来たの?』と、私を宇宙人みたいなものだと思っている子がいます(笑)」
自分が家族だと思えばその人は家族。
3つの家族からスタートした村
実は以前から観光地ではドラッグや売春の問題が根強く、鈴木さんは地元の人々と連携しながら、村の子どもたちを守ろうとサポートし続けている。
「でも、コロナ禍を経た今、またひどくなっています」
他にも、家庭環境に問題がある場合も少なくない。
「両親がいつもケンカしていたり、お兄ちゃんが酔っ払って帰ってきて暴れていたり。だからカノア保育園では、朝登園してきたとき子どもたちが自由に絵を描けるように、テーブルの上に紙とクレヨンを用意しています。そうすると、いろいろな家庭環境がある中で、言葉でうまく表現できない子どもたちが紙の上で気持ちを発散させたり、キレイな絵を自分で描いて自分を落ち着かせたりする。『今日のこの子の絵はいつもと違うなあ』と思ったら、すぐ『何かあった?』とコミュニケーションをとっています」
そもそも“家族の概念”が日本とは違うんです、と鈴木さんは続ける。
「子どもがいて、両親がそろっているひとつの家族より、お母さんはひとりだけどお父さんはいろいろ変わって4人いる、といったパターンが多い。そういう場合は、子どもはたいていおじいちゃんおばあちゃんの家に住んでいて、お父さんと言える人はおじいちゃんだったりします。例えば小学校に入って、『家族の人から仕事について話を聞いてきてください』という宿題が出されると、村の子どもたちは血縁関係の無い、ただ自分を可愛がってくれる大人に話を聞いてきたりする。つまり、自分が家族だと思えばその人は家族、ということなんです。最初エステーヴァン村は3つの家族からスタートしたので、元をたどればみんな親戚。それもあって、根底には“みんな家族”という意識があるんだと思います」
ちなみに、村の人口は鈴木さんが開園した2000年から現在に至るまで、ほぼ変わらず約300人なのだそう。村の長老に聞いてみたところ、「昔はひとりの女性が子どもを10人くらい産むのが普通だった。自給自足だったから、労働力としても子どもはたくさん必要だった。今は、ひとりの女性が多く産んでも4、5人。それでも人口が変わらないのは、村の外から来る女性と村の男性が結婚することが多いから。あなたみたいにね」と言われたそう。
「スマホも外部から入ってきて、村の人々は以前よりいろいろなことを知ることができるようになりました。『今までとは違うことを子どもたちに教えてあげてほしい』と、保育園に求める親が増えてきています。そのたびに私は、『今の先進国は、かつて未就学児のときから知的教育を高めようと”早期教育”、いわゆるお勉強に力を入れていたけど、今は”遊びの中で学ぶ”方向に変わってきている。私たちカノア保育園は、すでに自然の中でダイナミックにその教育ができているのだから、わざわざその素晴らしい伝統を壊すのではなく、大切にしていこう』と、日々話しているところです」